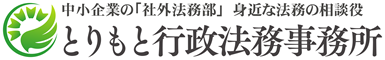雇用契約を結ぶより「業務委託」にしたほうがいろいろ楽って本当ですか?

2017年2月6日の朝日新聞に、こんなタイトルの記事がありました。
”非常勤講師「労働者と認めて」 救済申し立て(*1) 東京芸大は「業務委託」”
記事の内容を簡単にまとめると、
- 多くの大学で、週に何コマかの授業しかを担当しない非常勤講師は、「雇用契約」ではなく「業務委託契約」を結んでいる。
- 東大で1000人以上、阪大でも約1000人の非常勤講師が「業務委託契約」になっている。
- 雇用契約ではないので、契約を簡単に打ち切ることができたり、労働者に与えられるべき権利が与えられないなどの問題がある。
- 大学側(企業側)にとっては、「業務委託」にするメリット(社会保険料負担がなくなる、無期雇用転換ルール適用外、消費税控除)がある。
- 契約がいつ打ち切られるかわからない、不安定な状況では、教育の質を保てないのではないか、という疑念がある。
という内容です。
さて、一般の事業でも「雇用」か「業務委託」かという話はよく出てくるお話です。
トラックドライバー、販売スタッフ、サービススタッフと業務委託契約を結ぶ。
すると企業は、雇用に比べて次のようなメリットが出てきます。
- 社会保険料を負担しなくていい(労働者側も社会保険を適用されたくない、と思う人もいるのでしょうが)
- 福利厚生を提供しなくていい
- 雇用だと辞めさせたい時に簡単に辞めさせられないが、業務委託は簡単に打ち切れる
- 5年以上契約を継続しても、無期雇用に転換しなくていい(1年契約のアルバイトなど、有期雇用を5年以上継続すると無期雇用に転換しなければならないルールがある)
- 賃金は消費税控除の対象ではないが、業務委託報酬は消費税控除の対象になる
- 労働者保護に必要なルール(時間、割増、休日など)を守らなくていい
なんだか企業にとっていいことばかりのように見えますが、もちろん、デメリットもあります。
それは、「雇用ではない」ことです。
もう少し具体的に言いますと、
- 手が空いていたとしても、委託した業務以外をさせることができない。
- 業務の内容や遂行方法について、逐一指示することができない。
- 配置転換や業務の変更ができない。
- 業務の内容によっては、依頼の受託、業務の実施場所や時間を指示(強制)できない場合がある。
雇用じゃないのだから当然なのですが・・・。
ところが実際、よく行われているのが、
業務委託のメリットを得るために、表面上は業務委託契約を交わしているが、実際は「何ら雇用とかわらないこと」が行われている
というケースです。
裁判所や労働基準監督署は、このような問題に直面した場合、雇用かどうか=「労働者性の有無」を判断するにあたって、
「業務委託契約書を交わしている」などという表面上のことはまったく重視しておりませんで、
1.仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無
依頼や指示を拒否する自由がどの程度あるか?
2.業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
業務内容や遂行方法について、使用者からどの程度具体的な指示を受けているか?
予定されている業務以外のことをやらされていないか?
3.勤務場所・時間についての指定・管理の有無
業務の性質から判断して、その必要がないにもかかわらず、場所や時間が指定され、拘束されていないか?
4.労務提供の代替可能性の有無
本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか?
本人の判断で補助者を使うことが認められているか?
5.報酬の労働対償性の有無
遅刻や欠勤、残業など、時間に応じて報酬が増減するか?
6.事業者性の有無
使用する機械、器具等を本人が所有している、もしくは負担しているか?
報酬は、単純に労務の提供に対する対価ではなく、事業者としてのリスク負担を見込んだものになっているか?
7.専属性の程度
他社の業務に従事することを制限されていないか?拘束時間が長く、事実上、他社の業務に従事することを制限されていないか?
報酬に生活保障的な要素が見受けられる固定給部分がないか?
8.その他
選考過程が社員の採用と同じか?
服務規律を適用していないか?
などの点を、総合的に考慮して判断が行われます。
ですから、業務委託のメリットが欲しいからといって、タイトルを「業務委託契約」「請負契約」「準委任契約」にした契約書を交わした上で、その委託先さんを従業員さんと同じような感じでお付き合いしていると、後々大変なことになるかも・・・・?
心当たりのある社長様、事業主様はお気をつけ下さいませ。
*1 救済申し立て
使用者によって不当労働行為が行われた場合、労働組合又は組合員は、都道府県労働委員会に対して、その救済を求める申立てを行うことができます。
労働委員会による審査(主張の聞き取り、証拠の整理、公開審問など)の上で、当事者に対して命令(救済命令、棄却命令)を出します。
実際は、審査の過程で和解になることがあります。
労働委員会の発した命令に不服がある当事者は、中労委に再審査の申立てをしたり、地方裁判所に命令の取消しを求める行政訴訟(取消訴訟)を提起することができます。