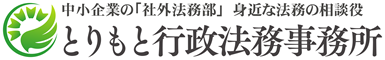風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その6

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もうシリーズ、第6回目です。
今日は、
第4 接待について(法第2条第3項関係)
を見ていきます。
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
(解説)
赤字で書いたことがすべてであり、大原則です。
単に「客をもてなす」だけであれば、ここで言う「接待」には当たりません。
では、「単に客をもてなすだけ」ではない、というのはどういうことかと言うと、
①特定の客又は客のグループに対して
②単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為
ということになります。(ただし、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」で、です。)
2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
(解説)
接待は、営業者や従業員だけでなく、芸者やホステス等が他所から派遣された者や、「客を装っているけど実態はサービスする役割の人」によるものであっても、接待となり得るし、接待する者の性別も問わない。
今日はここまで。