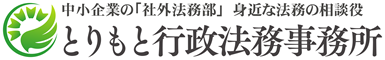(大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?⑧

大阪市で民泊事業をする場合、
A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業
この3つの制度のいずれかを選択することになります。
「選択する」と言いましたが、場合によっては、
「選べない」
「選択肢が消えて1つしか残らない」
ことも多いです。
このシリーズでは、3つの制度を比較しながら、どのような場合に「できる」「できない」のか、見ていこうと思います。
8回目の今日のテーマは「必要な設備」です。
3つの制度の「タテマエ」の違いが、一番はっきりくっきり表れているのが「必要設備」ではないかと思います。
A.旅館業
・寝具
・換気、防湿設備
・採光設備(つまり窓)
・照明器具
・排水設備
・入浴設備
・洗面設備
・トイレ
旅館業は、健康的に宿泊させることが求められていますので、以上のような設備等が必要になります。
「民泊」の規模と変わらない旅館業の場合はあまり問題になりませんが、複数のグループが同時に宿泊するような形態(例えば「民宿」)だと、トイレ、浴室、洗面の設け方が問題になります。
各部屋に設けられている場合はいいのですが、共同トイレ、共同浴室、共同洗面の場合は、数や男女の別等のルールがあります。
B.特区民泊
・台所
・トイレ
・浴室
・洗面
・テーブル
・椅子
・収納家具
・調理器具
・清掃器具
・冷暖房器具
・施錠設備
特区民泊のタテマエは「建物の短期賃貸借」ですので、滞在中の掃除や食事の準備等は滞在者が自らする、いえ、「させる」ということになります。
なので、滞在者が自ら「できる」ような設備が求められます。
また、単に宿泊させるだけではないので、数日から1週間ほど滞在できるよう、テーブルやいす等も求められます。
C.住宅宿泊事業
・台所
・トイレ
・浴室
・洗面
住宅宿泊事業は、旅館業同様、宿泊させることが求められるのですが、食事の準備は宿泊者がすることも考えられる(ホストが食事を提供するには飲食店営業の許可が必要)ので、台所が必要設備に加わります。
また、住宅宿泊事業は、家主と宿泊者、家主と複数の宿泊者が滞在することを前提にしているので、「1つの台所をみんなで使う」ということが可能になっています。
※わかりやすくするため、専門用語を使わず大雑把に説明していますので、詳細はご確認下さい。