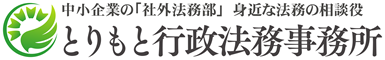契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説①「当事者の特定」

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
契約書を作ったり、内容をよく読んだりするときの注意点を説明するシリーズの第1回目のテーマはこちら。
「契約当事者の特定」
です。
契約書の内容も大事ですが、
・そもそも誰と誰がその約束をするのか(場合によっては3名以上かもしれません)
・その人は実在するのか
これが一番大事です。
仮に契約の相手が目の前にいる人だとしましょう。
いや、その前に、そもそも「その目の前の人と、契約書の乙だか甲だかという人は、本当に同じ人」なのでしょうか?
こういう場合は、公的な機関が発行している、できれば顔写真付きの身分を明らかにできる何かを提示してもらい、確認しましょう。
(例:運転免許証、パスポート)
もっと慎重に確認したい、ということであれば、「印鑑証明書」を提示してもらうことです。
印鑑証明書は、「その人しか持っていないはずの印鑑の印影」と「印鑑所有者の氏名、住所、生年月日」を証明するものです。
契約書に押す印影と印鑑証明書の印影が合致すれば、その契約書は間違いなく本人が捺印したもの、ということになりますよね。
これは、相手が法人(会社)であっても同じです。
※もちろん、契約書に押す印鑑は、実印(登録印)でなくても、認印でも有効です。
いきなり脱線してしまいました。次のポイントに行きます。
契約書に書かれている相手方の情報は正しく記載されているでしょうか?
後から第三者が見ても明確な契約書にするためには、契約当事者が誰なのか、特定されていなければなりません。
ですから、氏名だけでなく住所も併記したいところです。同姓同名の人がいるかもしれませんしね。
提示してもらった証明書と見比べて、違いがないか確認して下さい。
念には念を、ということなら、生年月日を併記してもいいかもしれません。
法人が契約相手なら、住所と会社名だけでなく、代表者の氏名も記載してもらいましょう。
法人の場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)で相手を確認するのがいいと思います。
登記簿謄本には、その会社の住所(本店所在地)、名称(商号)、代表者(役員)の氏名が記載されています。