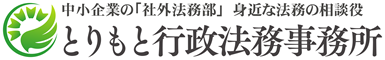市街化調整区域で民泊はできるか?

今日のテーマは、
「市街化調整区域で民泊はできるか?」
です。
先に言い訳がましいことを申し上げておきます。
市街化調整区域内の既存建物の取扱いについては、自治体の独自色がかなり強いので、ここで書かれていることがすべての自治体において通用するとは申し上げられません。
また、このブログでは「できるだけわかりやすく」を旨としておりますので、表現が正しくない可能性があります。
■市街化調整区域の基本
市街化調整区域というのは、自治体が「このエリアは街にしたくない」と考えている場所です。
ですから、基本的には建物を建てられませんし、例外的に建てられた建物も用途を強く制限されます。
では、「例外」というのはどういうものでしょうか?
A.いわゆる「属人性」のない例外
①その場所が市街化調整区域に指定される前からある建物
②「既存宅地確認制度」「建築を許容する制度」によって建築された建物
B.いわゆる「属人性」のある例外(基本的に住宅)
①農業、林業、漁業に従事する者のための住宅
②そこに住んでいた世帯の構成員が新たに建てた分家住宅
③土地収用などが原因で、移転された住宅
よく問題になるのは「属人性のある建物」です。
これらは、特定の人や世帯が住むためのもので、それ以外の人が住む、別の用途に使うなどはできません。
■旅館業、特区民泊
旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所等)に使用する建物は、建築基準法上(用途変更の要否にかかわらず)「旅館」などの用途となります。
属人性のある建物は、原則としてこれらの用途に使用することはできません。
属人性のない建物でも、観光資源の鑑賞等のため必要などと認められない限り使用できません。
また、特区民泊は、その事業を行える場所が制限されており、市街化調整区域はできない場所になっています。
■住宅宿泊事業
住宅宿泊事業に使用する建物は、建築基準法上「戸建住宅」などの住宅系の用途となります。
先述した通り、市街化調整区域の既存建物は「例外的に」許されて建てられています。
「Aさんが住むために特別に許されて建てた住宅」を、家主不在型住宅宿泊事業に使用するとなると、Aさんはそこに住んでいないということですから、「特別に許されたのはどこへ行っちゃったの?」ということになります。
市街化調整区域で民泊を検討する際は、慎重に確認をして下さい。
この件については、保健所に相談・・・・よりも、建築指導や開発を担当する窓口のほうが速くて正確かもしれません。