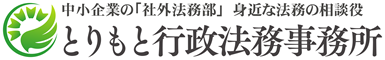特区民泊に必要なもの、建築基準法編 その①

建築基準法は、一般の方が理解するにはちょっと難しすぎる内容です。
正直申し上げて、私も全部は理解していません。
民泊に関係する部分を理解したようなつもりになっているだけです。
ですので、よりプロフェッショナルな知識や経験を要する場合は、その筋の専門家、建築士の先生などにご相談することになります。
しかし、スタンダードな民泊をするのに、「何が障壁となるのか」「どれくらいの大きさの問題なのか」「どれくらいのコストで問題解決できるか」くらいは建築士の先生にお尋ねしなくとも回答することはできます。
①建築基準法上の「用途」のお話
「用途」とは、その文字通りの意味で「どういう使い方をしているのか」とご理解頂ければよろしいかと思います。
建築基準法では、その建物の利用者の安全のために、建物の用途ごとに具体的規制を設けています。
戸建住宅には戸建住宅の守るべきルールが、ホテルにはホテルの、学校には学校の、公衆トイレには公衆トイレのルールがあり、これに沿った措置が必要です。
さて、特区民泊を行う建物、または建物の一部分は、建築基準法上、その形質に合わせて「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」として扱われます。
この一文の意味をかみ砕くと、次のようになります。
特区民泊を始める前は、その建物の用途は何だったの?
「住宅」、「長屋」、「共同住宅」、「寄宿舎」の住居系の用途だったらいいのだけれど、
「事務所」とか「店舗」とか「倉庫」とかだったら、そのままではまずいかもしれないね。
ということになります。
「まずいかも」というのは、場合によっては手続きや工事が必要になるかもしれない、ということです。
②非常用照明装置の設置
非常用照明装置というのは、
・バッテリーがあって停電したときに機能する
・耐熱性があって火事があっても光る
ようなものです。
早い話が「夜間火事になって、炎で電気の線が焼けて停電しても、安全に逃げられるよう足元を照らす装置」です。
次のような場合を除いて設置が必要です。
①寝室が1階の場合、イ、ロ両方クリアしている。
イ、寝室の奥から玄関まで30m以内。
ロ、寝室から玄関まで光の入る窓がある。
②寝室が2階の場合、イ、ロ両方クリアしている。
イ、寝室の奥から玄関(又は屋外避難階段)まで20m以内。
ロ、寝室から玄関(又は屋外避難階段)まで光の入る窓がある。
③床面積が30㎡以下の居室で、直接地上へ逃げられる。
④床面積が30㎡以下の居室で、地上に逃げられるルートに非常用照明装置が設置されているか、外気に開放されている。
※民泊施設内の部屋を一部屋ずつ上記①~④に該当するか否か検討する必要があります。