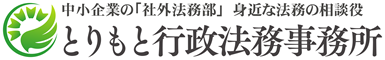風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その3

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もうシリーズ、第3回目です。
今日読むのは、
第3 ゲームセンター等の定義について(法第2条第1項第5号関係)
です。
この「第3」を今回1回で終わらせるのはおそらく無理なので、何回かに分けることになりそうです。
1 趣旨
本号は、ゲーム機賭博事犯や少年非行の温床となるおそれのあるゲームセンター等を風俗営業とすることにより、その健全化と業務の適正化を図ることとするものである。
(解説)
解説するまでもなくこのままですね。
ゲーム機賭博事犯や少年非行の温床にならないように、ゲームセンター営業を風俗営業に定めて、健全化・適正化を図りますよ、ってことです。
2 遊技設備
本号は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)」を設置して客に遊技させる営業を対象とする。
(ここまで一旦切って解説)
4号営業(マージャン店、パチンコ店)と5号営業(ゲームセンター等)を合わせて「遊技場営業」と言います。
5号営業(ゲームセンター等)と4号営業(マージャン店、パチンコ店)との違いを、誤解を恐れず端的に言うと、
・4号営業=「ギャンブルのための設備、例えば、パチンコ台やマージャン卓を設けて遊ばせる営業」
・5号営業=「基本的にはギャンブルのための設備じゃないんだけど、使い方によってはギャンブルに転用できてしまいそうな設備を設けて遊ばせる営業」
という感じになります。
分かりにくいのは「使い方によってはギャンブルに転用できてしまいそうな設備」ですが・・・。
(以下、本文続きです。)
具体的な遊技設備は、施行規則第3条に定められている。
スロットマシン、テレビゲーム機等で遊技の結果が定量的に表れるもの又は遊技の結果が勝負として表れるものや、ルーレット台やトランプ台等賭博に用いられる可能性がある遊技設備は対象となるが、占い機で盤面にインプットすべき内容を指示する程度にとどまるもの等これら以外の遊技設備は、対象から除外される。
また、遊技の結果が定量的に表れ、又は遊技の結果が勝負として表れる遊技設備であっても、単に人の物理的力を表示するもの等については、「射幸心をそそる遊技の用に供されないことが明らかなもの」として対象から除外することとしているが、この規定は通常のインベーダーゲーム機等を対象から除外するという趣旨ではない。
なお、
① 実物に類似する運転席や操縦席が設けられていて「ドライブゲーム」、「飛行機操縦ゲーム」その他これに類する疑似体験を行わせるゲーム機(戦闘により倒した敵の数を競うもの等、運転や操縦以外の結果が数字等により表示されるものを除く。)
② 機械式等のモグラ叩き機
については、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
(ここまで一旦切って解説)
ギャンブルに転用できそうな遊技設備というのは、
・ゲームの結果が「数字」で表れるもの(どんなゲーム機でも「点数」「スコア」等の数字で、プレイの上手下手を表す数字を表示する仕組みになってますよね。)
・ゲームの結果が「勝敗」で表れるもの(対戦格闘ゲームとか、マージャンゲーム、ポーカーゲームを指します。)
・ルーレット台やトランプ台等(そのままギャンブルに転用できる。)
を指します。
早い話が、これらのゲームの「数字」や「勝敗」に対して賞品や賞金を出すような営業は、正に賭博場営業そのものと言えますよね。
だからそうならないように、そうさせないために「規制の対象にするよ」ということです。
そういう考え方で行くと、
・占いゲーム(占いの結果でギャンブルしようっていう発想になかなかならない)
・パンチ力やキック力を測るゲーム(「力が強い奴が勝ち」ってギャンブルではないですよね)
は、ギャンブルに転用することが考えにくいので、規制の対象にはしないとされています。
また、
・点数等が表示されない「ドライブシミュレーター」や「フライトシミュレーター」
・機械式のモグラ叩きゲーム
は、今のところ、ギャンブルへの転用や、少年への悪影響の問題につながっていないし、つながりそうもないので、今のところは規制の対象から外して様子を見る、ということです。
(機械式のモグラ叩きに熱中してたむろする少年たちを想像すると、ちょっとほっこりしませんか?)
本日はここまで。