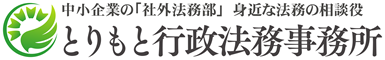契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説⑤「信義則」

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
契約書を作ったり、内容をよく読んだりするときの注意点を説明するシリーズの第5回目のテーマはこちら。
「信義則条項」
です。
「信義則」というのは略語で、正しくは「信義誠実の原則」と言いまして、
「私的取引関係において、相互に相手方を信頼し、誠実に行動し、裏切らないようにするべき原則」
という意味です。
信義則は、法律や契約で明確にされていない事柄であっても、信義誠実に行動するべきだから、**のようなときは「○○するべきだった」「××するべきではなかった」と判断をする根拠になる原則です。
できるだけわかりやすい例え話をしようと思います。
A君とB君は、あらかじめX月XX日に会う約束をしていました。
約束の日の前日、A君はB君に「明日は10時に梅田で待ち合わせしよう」とメッセージを送りました。
しかし当日、B君は「梅田のどこやねん?」と思い、待ち合わせには行きませんでした。
確かにA君の発言には曖昧すぎるという落ち度がありますが、B君が信義誠実に行動していたなら、「梅田のどこにする?」と聞いているはずで、少なくても約束を一方的に反故にするべきではなかったですよね。
とまあ、こういうことです。
実際に契約書ではどのように使われるかと言うと、
第X条(基本原則)
甲及び乙は、甲乙間の取引が相互の信頼に基礎を置くものであることを認識するとともに、乙は本契約の委託業務の遂行にあたり、誠意と責任をもって迅速且つ安全・確実に契約を履行しなければならない。
第X条(信義則)
甲及び乙は、本件業務が相互の信頼に基づくものであるとの認識を共有するとともに、本件業務の遂行が甲乙両者間の誠意ある協力の上に成り立つこと確認する。乙は上記確認に基づき、甲が委託する業務の遂行にあたり、甲の指示に従い誠意をもって適正、正確、迅速に本契約を履行しなければならない。
こんな感じです。
で、契約書にこの信義則条項を設ける意義ですが・・・・・
皆無です。
なぜなら、この信義則は、民法第1条第2項に規定されている、当然の原則ですから、わざわざ契約書に書かなくても適用されるからです。
民法第1条
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
よほど書きたい理由があるなら、書いておいたらいいと思います。