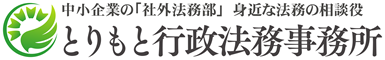同業者(厳密な意味で)と話すのも面白い

タイトルの「厳密な意味で」についてですが・・・・。
私は、我々行政書士にとって、「同業者」というのはかなり「意味のあいまいな言葉」だと思っています。
「同業者」という言葉を使う状況によって、「大」「中」「小」というか、「松」「竹」「梅」というか、それくらい意味が変わってきてしまうのかな、と。
同業者(大)
これは、他士業者を含めた「士業者」というくくりです。
弁護士、司法書士、社労士、税理士、弁理士などの平たく言えば「資格を持って法律を扱う生業をしている人」という感じですかね。
この言い方だと、「どんな専門的資格を持っているか、どんなフィールドで活躍しているか」はあまり関係なくて、広く「法律系サービス業者」という共通点しかありませんので、「同業者(大)」の間では相互に分かり合えないことがたくさんあります。
同業者(中)
これは、「行政書士」というくくりです。
客観的な意味で、純粋な意味での「同業者」ということになるでしょうか。
この言い方だと「行政書士という仕事ができる人」という共通点を持つ人を指すわけですが、行政書士が取り扱う業務は非常に幅が広く、「私はすべての行政書士業務ができます」という人を見たことも聞いたこともありませんし、「ある業務を、A行政書士は取り扱っているが、B行政書士は取り扱っていない」というようなことが当たり前にあります。
同業者(小)
これは、「取り扱っている業務を同じくしている行政書士」というくくりです。
行政書士にとって、本当の意味での「同業者」と言えるのではないかと思います。
例えば「建設業の許可関係を取り扱っている行政書士はたくさんいる」けれど、「民泊の許可関係を取り扱っている行政書士は多くはない」です。
前者のグループと後者のグループでは、言葉が通じないほど、「別の人種」って感じです。
長い前振りになってしまいました。
今度、同業者(小)の方と一緒に、「宿泊事業に関する手続き」をテーマに研修をすることになりまして、先日準備のための打ち合わせをしてきました。
結論から言うと
「めっちゃ楽しかった」
です。
行政書士は、通常、複数人で組んで業務を進めるということはほとんどありません。
例外的に、「先輩と後輩」「経験豊富な人と不慣れな人」というような「一方が教えを乞い、一方が教える」という形態がありますが、全体の件数から見ればかなり稀です。
だから、自分以外の仕事のしかたを知ることがほとんどない。
ところが、研修の準備となると、
「どんな内容の話しましょうか?」「時間配分は?」「配布資料は?」
なんていう大枠のお話もあるけれど、
「この部分はどこまで深堀して説明しますか?」「実務上の注意点とかどこまで丁寧にします?」
みたいなかなり突っ込んだ話もする。
そうすると、すぐ脱線して
「手引きとかには書いてないですけど、ぶっちゃけこういう問題もありますやん、先生は普段どうされてるんですか?」
「私、以前こういうことがあったんですよ、だから、こういう時はこういうことに気をつけてます。」
「でも、その話は具体的過ぎて研修では話せないですよね。」
みたいな情報交換になってしまう。
めっちゃ楽しい。
具体的な話はできませんけど。